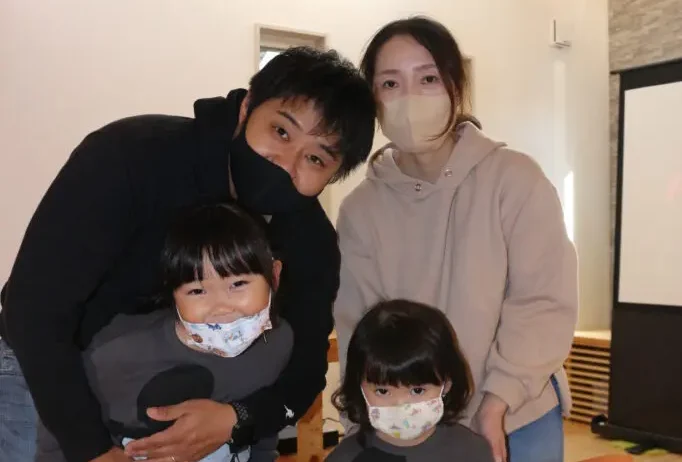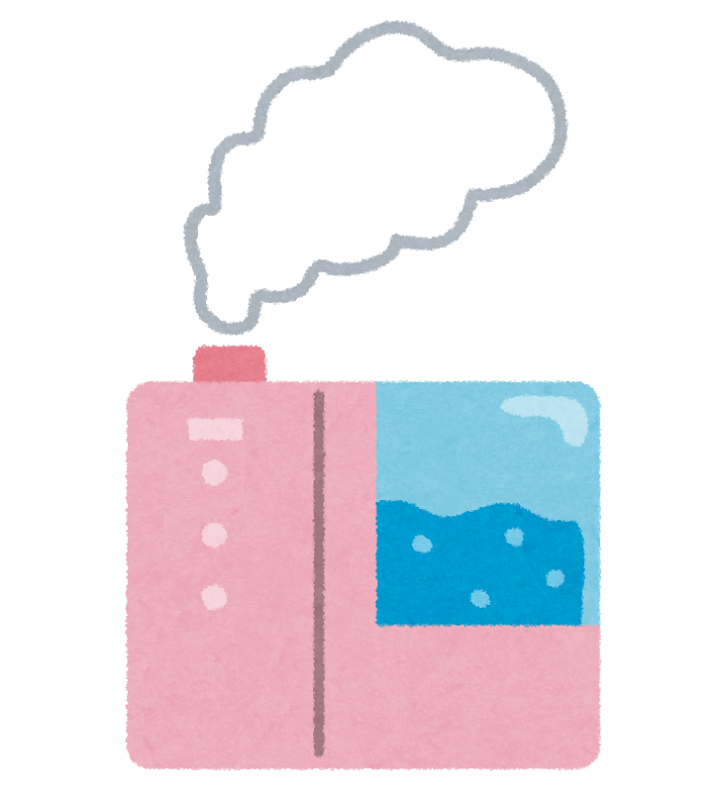「地震による地盤の被害にどう備えるか?」
住まいづくりにおいて一番と言って良いほど
関心のあるテーマについてお伝えします。

今だ復旧作業が継続中の能登半島地震の
爪痕ですが、地震災害の大きさを感じます。
この大きな地震を受け、地盤への備えの
重要性があらためて見直されています。
これまでも耐震構造の大切さについて
お伝えしてきましたが、
地震に強い家を建てるうえでは
「どんな地盤の上に家を建てるか?」
という視点も欠かせません。
今回はその地盤に焦点を当てて解説します。
地盤被害って何?液状化って?
「地盤被害」と聞いてピンとこない
方もいるかもしれませんが、
報道などで「液状化現象」という
言葉は耳にしたことがあると思います。
例えば、1995年の阪神淡路大震災で
神戸のメリケンパーク周辺が液状化し、
地面がグチャグチャになったことがありました。
また、千葉のディズニーランド近くや、
新潟でも液状化被害がたびたび報告されています。
地震による主な地盤被害の3種類
地震による地盤被害は、大きく分けて以下の3つに分類されます。
① 土砂崩れ(+津波)
山や崖の近くでは、地震によって斜面が崩れ、
大量の土砂が流れ込む危険があります。

また、津波も地盤条件により被害の大きさが異なります。
② 地割れ
漫画のように地面がパックリ割れる現象。

実際に家が沈んだり、車や人が
落ちてしまうケースもあります。
③ 液状化現象
砂質土の地盤に多く見られ、
地震によって砂粒の隙間にある水分が
押し出され、地面が一時的に
液体のようになってしまう現象です。

家が傾いたり、水道や下水の配管が
破損する原因になります。
被害を防ぐための第一歩:ハザードマップの確認
地盤災害の備えとしてまず行いたいのが、
ハザードマップの確認です。

洪水リスクを見る人は多い一方で、
地震・液状化・土砂崩れ・津波の
ハザードマップを見る人は意外と
少ない印象です。
しかし、能登の地震でも、
実際に被害があったエリアは
ハザードマップで警告されていた場所でした。
➤ ポイント:
ハザードマップは「伊達や酔狂」で作られているわけではありません。
土砂災害・津波のリスクが高い場所では、そもそも住むべきかを再検討する必要があります。
液状化リスクはどう見極める?
液状化が起こりやすいのは、
砂質土の地盤、特に海や川の
近くにあるエリアです。

確認方法①:地形と地質をチェック
Googleマップの航空写真や地形図で、かつて川や海だった場所かを確認
例えば広島のような三角州エリアは要注意
確認方法②:液状化の履歴を調べる
過去に液状化が発生した記録があるエリアは、再発の可能性も高いです
地盤調査のススメ:スクリューウエイト貫入試験
家を建てる際には、
「スクリューウエイト貫入試験(SWS試験)」
という方法で、地盤の強さを調べることができます。

T字型のドリルで地面にねじ込みながら
重りを載せて、沈む深さや抵抗を
測定する簡易的な方法ですが、
非常に精度が高く、液状化リスクの判定にも使えます。
液状化への対策は?2つのアプローチ
液状化対策としては、大きく分けて以下の2つの方法があります。
① 液状化が起こりにくい地盤に改良する
地中の水を抜くなど、大掛かりな工法
公共施設向きで、個人宅ではコスト面から難しい場合も
② 液状化しても家が沈まない構造にする
「柱状改良」や「鋼管杭」で、深い硬い地盤まで支柱を届かせて支持力を確保
地盤が緩くても、家を支えることが可能
傾いた家も復旧可能なケースがある
地盤の粘土層などによって家が傾く
「圧密沈下」が起こった場合でも、
しっかりとした基礎と構造を持つ家であれば、
ジャッキアップで復旧可能です。

つまり、耐震性能の高い家づくりは、
地盤被害に対しても有効な備えとなります。
安全な家づくりには「地盤対策」が必須
これから家を建てる、あるいは建て替える方は、
建物の耐震性能だけでなく、土地の地盤特性を
よく調べてください。
ハザードマップを見る
液状化履歴を調べる
スウェーデン式サウンディング試験を活用する
必要に応じて地盤改良を検討する
安全な暮らしのために、地盤対策という
視点をしっかり持って、地震に強い
家づくりを実現しましょう。