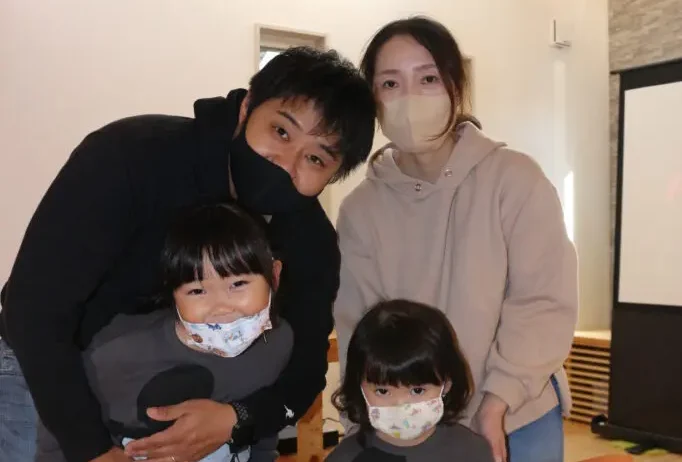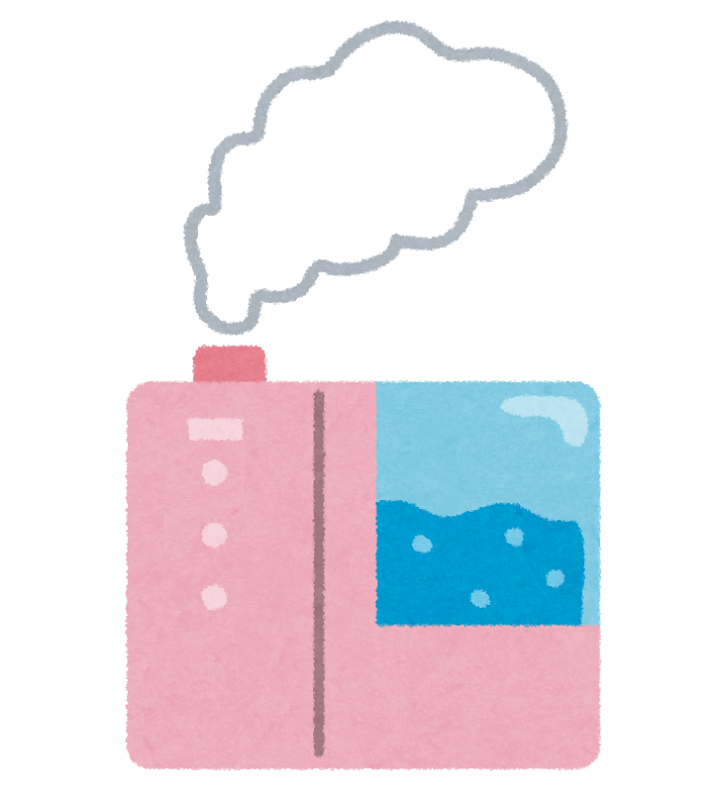住宅設計において「太陽に素直な家づくり」は、
住まいの快適性と省エネ性を大きく左右します。
今回は、なぜ「夏至と冬至」ではなく「大暑と大寒」で考えるべきなのか。

建築家・辻先生の著書
『ぜんぶ絵でわかるエコハウス』をきっかけに再認識した、
大切な視点をお届けします。
私の住宅設計の原点「太陽に素直な家をつくりなさい」
住宅温熱環境の専門家の松尾和也先生から、
こんな教えをいただきました。
「太陽に素直に家を作りなさい」
これは、自然の力を味方にした設計思想です。

そしてその実践のために、
まず意識すべきは「夏至」と「冬至」だと教わりました。
夏至は1年でもっとも太陽高度が高く、
日照時間が長い日。
冬至は逆に、もっとも太陽高度が低く、
日照時間が短い日。
この2つの極を踏まえて、
窓の位置や庇(ひさし)の出幅を設計することで、
太陽光のコントロールを行うという考え方です。
しかし…気温のピークは夏至・冬至ではない?
建築を学び続けていく中で、
私はこう考えるようになりました。
「夏至と冬至だけでは不十分なのでは?」
そんな中、出会ったのが辻先生の著書
『ぜんぶ絵でわかるエコハウス』でした。
この本の中に「夏は大暑で、冬は大寒で考えるべき」という視点があり、
非常に腑に落ちたのです。
二十四節気で読み解く、気温と太陽の関係
日本には美しい季節の表現「二十四節気」があります。
その中で、
大暑(7月23日頃):1年で最も暑いとされる時期
大寒(1月20日頃):1年で最も寒いとされる時期
とされています。
実は、気温のピークは「夏至」「冬至」ではなく、
これら「大暑」「大寒」なのです。
これは、地表が太陽熱を吸収して温まる/冷えるまでにタイムラグがあるためです。
太陽高度と庇(ひさし)の関係
例えば、太陽高度は以下のように変化します(日本の緯度35度前後を想定):
夏至の太陽高度:約78度(ほぼ真上から)
冬至の太陽高度:約32度(斜めから差し込む)
白露(9月上旬):約61度
春分・秋分:55度程度
この変化に応じて庇の設計を最適化しなければなりません。

一般的には、
“窓の高さを10とした場合、庇を3出す(10:3の比率)”のが理想とされていますが、
それも「夏至基準」の話です。
大暑・白露・秋分を意識した設計のすすめ
実際には、暑さのピークは7月下旬〜9月中旬にかけて続きます。
この間にしっかりと日射遮蔽できないと、
エアコンの効きが悪くなり、
光熱費が無駄にかかります。

ですので、
夏は 芒種〜秋分 くらいまでを遮蔽設計の対象にする
白露(太陽高度約61度)でも遮れる庇 or アウターシェードの活用が有効
と考えることが、より実用的です。
実際の敷地は「真南向き」でないことが多い
理論上は、真南向きの窓に対して庇を最適化しますが、
実際の敷地条件では東向きや西向きにずれているケースが多々あります。
その場合、太陽の入射角はさらに変化し、
庇だけでは対応しきれないことも。
そのため、
アウターシェード
すだれや葦簀(よしず)
外付けブラインド
などを併用して、柔軟に遮蔽する工夫が大切です。

これからの家づくりは「大暑と大寒」で設計する時代へ
「太陽に素直な家づくり」とは、
ただ夏至・冬至を基準に考えるのではなく、
気温のピーク=大暑・大寒に合わせて最適化することです。
✅ 夏のピークは 夏至ではなく大暑
✅ 冬のピークは 冬至ではなく大寒
✅ 庇だけでは限界。アウターシェードなど複合的に考えること
✅ 季節の移ろいを感じながら暮らせる設計を目指すこと
こうした考え方を取り入れることで、
本当に快適な「太陽に素直な家」が実現できるはずです。
これから家づくりを考える方は、
ぜひこの視点を持って住まいづくりに臨んでみてください。