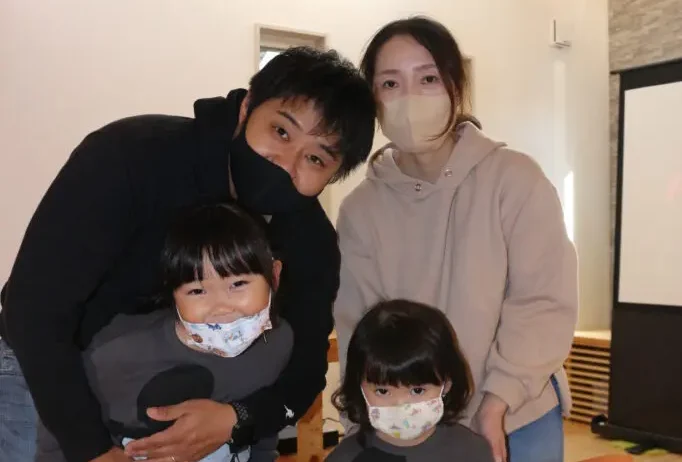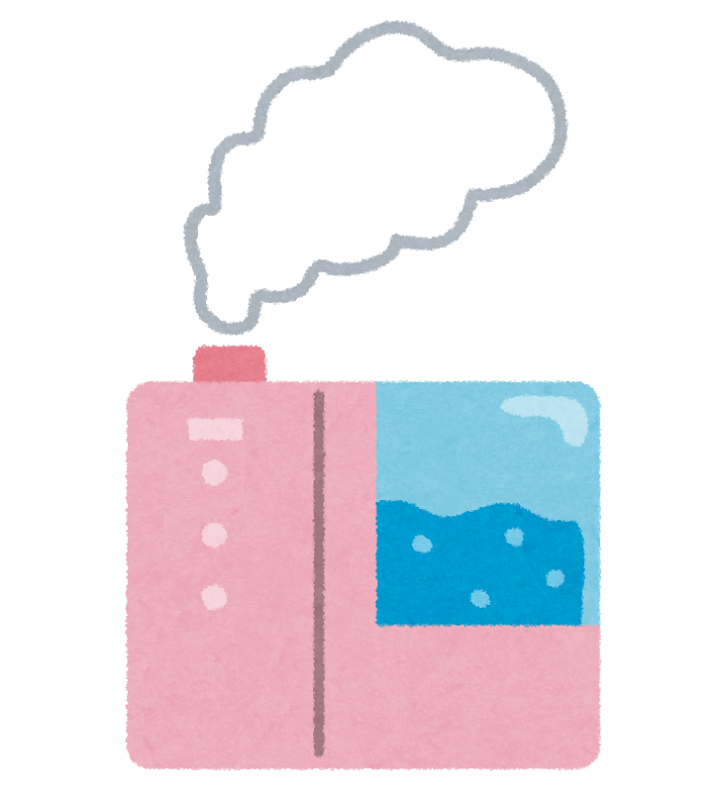以前にもアップした記憶がありますが、
もっと端的に表現する方が
みなさんに分かりやすいのではと思い、
再度【60年保証】について書いてみます。
家づくりを考えるとき、多くの方が
気になるのが「保証」の話です。

特に若い世代であれば、家を建ててから50年、
60年と住む可能性があります。
だからこそ、保証は非常に大切なテーマです。
今回は、家の保証の基本から、
よく耳にする「60年保証」の実態まで、
わかりやすく解説します。
瑕疵保証は10年、これが法律で義務付けられている
まず知っておいてほしいのは、国の法律で
定められている「瑕疵(かし)保証」です。
家の引き渡し後10年間、構造上の欠陥や
雨漏りといった重大な不具合に対して
保証する義務があります。

この10年間の保証は、すべての
住宅会社が必ず付けています。
ただし注意が必要なのは、
この保証はあくまで「構造的な欠陥」に
限られるということ。
たとえば電気が点かない、
床が傷ついた、壁紙が剥がれた
──こうした生活上の傷や劣化は対象外です。
イメージとしては、車の保証でいう
「エンジンの不具合」であり、
「ブレーキパッドの摩耗」や
「タイヤのすり減り」ではありません。
長期保証の実態 ─「60年保証」は無条件ではない
次に気になるのが、「60年保証」といった
長期保証の話です。
一見、「60年間ずっと家を守ってくれるの?」と
思ってしまいそうですが、
実際はそうではありません。
多くの住宅会社では、最初の10年間の
無料保証が終わった後、
10年ごとに保証を「更新」していく
仕組みを取っています。
その際、5年ごとに点検があり、
指摘された修繕をきちんと行うことが条件です。

つまり、保証継続のためには
定期点検を受ける
指摘された箇所を修繕する
というステップを繰り返す必要があります。
これを続けることで、最長60年保証が
「可能になる」わけですが、
何もしないで60年守って
くれるわけではありません。
保証の注意点 ─ 過剰な修繕や保証料の現実
もう一つ大切なのは、
保証の性質を正しく理解することです。
保証する側(住宅会社)も、
なるべく大きな修理費用を
負担したくありません。
そのため、場合によっては
「ここまで直せば十分」という基準を
超えて、「念のため、ここも直しておきましょう」と
過剰に修繕を求められるケースもあります。
また、更新のたびに保証料が必要になります。
そのため、保証を続けることで
安心は得られますが、場合によっては
無理に保証に頼らず、
必要なときに必要な修繕を行うほうが
合理的なこともあります。
メンテナンスコストのかからない家を目指す
もっと理想的なのは、最初から
メンテナンスコストがかかりにくい家を
建てることです。

例えば、高耐久の外壁材や、
メンテナンスしやすい屋根材を選ぶなど、
家そのものの性能を高めておけば、
わざわざ保証料を払い続ける必要が
なくなります。
賢い保証との付き合い方
・10年の瑕疵保証は法律で義務化されている
・60年保証は「無条件」ではなく、定期点検・修繕・保証料が必要
・保証内容は構造に限られ、生活上のトラブルは対象外
・メンテナンスコストのかかりにくい家づくりが長い目では有利
保証を過信せず、必要なときに
必要なメンテナンスを行う。
そして最初の設計・施工段階で
耐久性の高い家を建てる。
これが、賢い家づくりの基本といえるでしょう。