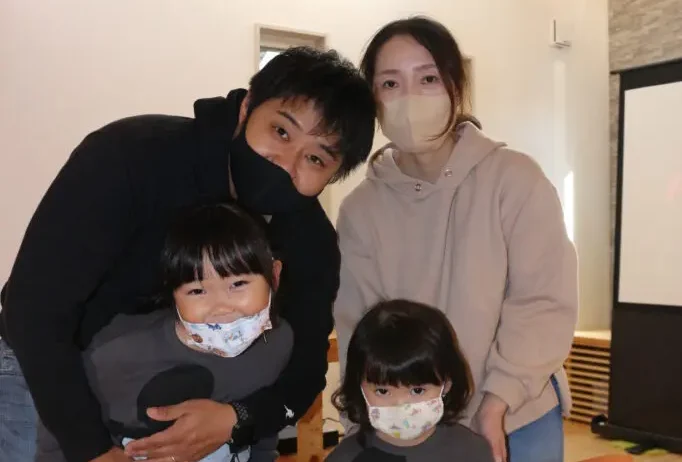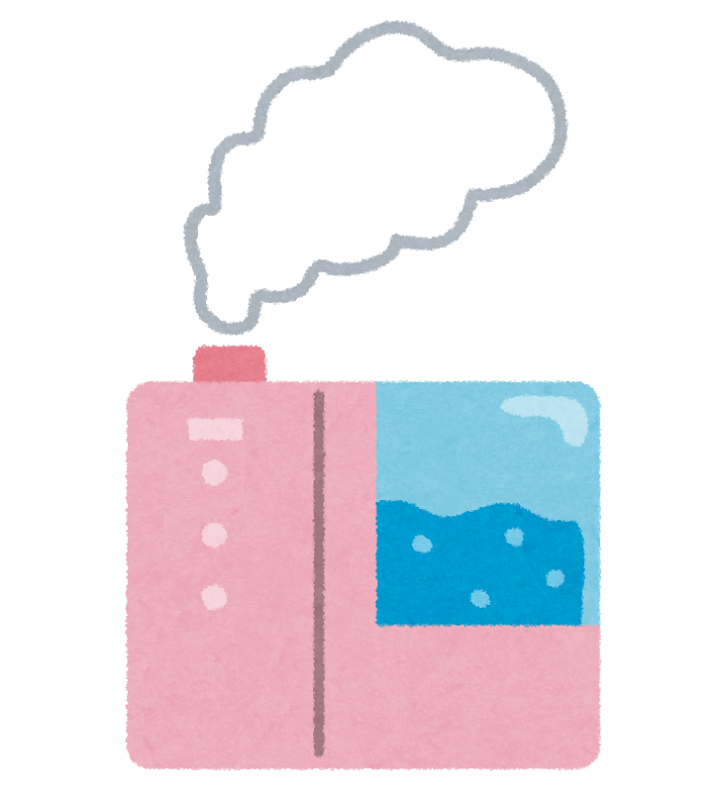阪神・淡路大震災以降、よく耳にするのが
「木造住宅は怖い」
「瓦屋根は地震に弱い」という言葉です。

しかし、こうした言葉には誤解が
含まれています。正しくは、
「耐震性能が十分でない古い建物に
瓦屋根が使われていた」というのが事実です。
瓦屋根は確かに重いですが、
建物がその重さに見合った耐震性能を
備えていれば問題はありません。
つまり、重さそのものが悪いのではなく、
それに耐えられる設計かどうかが重要なのです。
瓦屋根と耐震性の誤解
構造塾の佐藤先生が人間の体格に例えて
分かりやすく説明されています。
50kgの人と100kgの人が同時に地震を受けた時、
100kgの人の方がより大きな地震力を受けます。
しかし、足(=構造・耐震性能)が太く
しっかりしていれば、重くても倒れにくいのです。

建物も同じで、重い屋根でも、
それを支えるだけの設計がされていれば
問題ありません。
古い木造住宅には、瓦の下に土を敷いた
「土葺き」が多く用いられ、
より重くなっています。
加えて、土壁や漆喰なども
壁の重量を増やしていました。
また1981年以前の建物は、
新耐震基準が施行される前に建てられており、
耐震性能が不足している場合が多いのも事実です。
地震の被害傾向:能登半島地震から学ぶ
能登半島地震では、震度7の第1波で
多くの家屋が倒壊しました。
これは、1981年以前の旧耐震基準の建物が多く、
さらに過去の地震によるダメージが蓄積されて
いたためです。

熊本地震のように、第2波で倒壊する
ケースもありますが、能登では最初の一撃で
命を落とす危険が高まりました。
珠洲市周辺は過去にも震度6強を
記録する地震があり、見た目には無事でも
構造が弱っていた建物も多かったのです。
自宅の安全性を見極める方法
家の安全性を判断するには、
建築年代が一つの指標になります。
- 1981年以前:旧耐震基準。最もリスクが高い。
- 1981年〜2000年:新耐震だが設計基準が現代より甘い。
- 2000年以降:四分割法やN値計算など、より厳格な基準に基づいて設計。
その上でおすすめしたいのが「微動探査」です。
これは、地盤や建物の揺れやすさを
実際の微小振動で測定する調査です。
地盤がしっかりしているか、建物が
どれくらい揺れるかなど、
数値で客観的に確認できます。

調査結果を見せることで、家族や親族を
説得する材料にもなります。
費用は10〜20万円程度です。
具体的な耐震補強対策
見極めが済んだら、必要な対策を講じましょう。
- 壁量のチェック
- 建物の床面積に乗数をかけて、必要な壁量を算出します。
- 屋根の重さによって乗数が変わります。
- 壁の配置バランス
- 壁量が足りていても、バランスが悪ければ倒壊リスクは高まります。
- 四分割法やN値計算でチェックします。
- 屋根の軽量化
- 重い瓦を軽量瓦やガルバリウム鋼板などに変える。
- 金物補強
- 柱頭・柱脚や筋交いの固定金物を追加する。
- 特に古い筋交いは釘1本で止まっているケースも。
- 開口部補強(門型フレーム)
- 商店やピロティ構造の家では、開口補強フレームを導入する。
- 基礎補強
- 延石や束石などの古い基礎には部分補強を行う。
命を守る家にするために
こうした対策は、専門家の協力が不可欠です。
調査・計算・補強計画すべてを
自己判断で行うのは危険です。
また、対策には時間とお金がかかりますが、
地震は予測できません。
元日のような誰もが油断している瞬間に
襲ってくる可能性があります。

命を守る住まいとは、単に倒壊しない
ことではなく、安心して長く暮らせること
でもあります。
寿命が延びる時代、安心できる家での
暮らしこそが、家族を守る最大の備えに
なるのではないでしょうか。
古い家が悪いのではありません。
無対策であることが危険なのです。
ぜひ、ご自身やご家族の住まいを
見直していただき、大切な命を守る行動を、
今こそ始めてください。