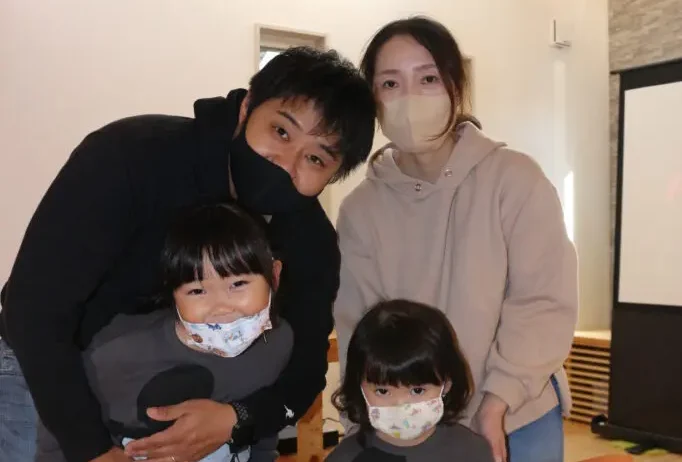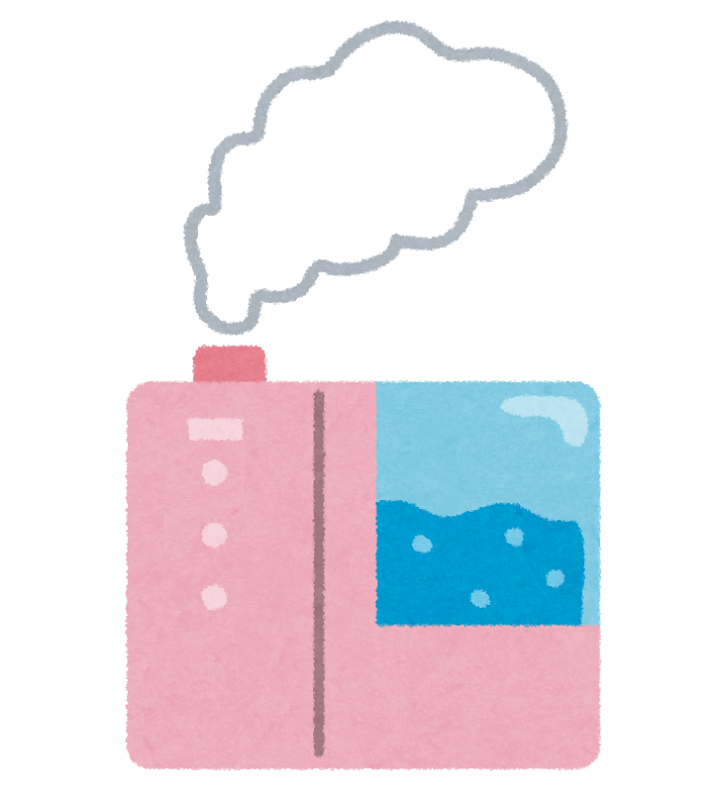家の快適性・省エネ性を測る1つの
指標として「C値(隙間相当面積)」という
気密性の数値があります。

この数値がどれくらいであればよいのか?
という質問をいただきましたので、
今回はその基準と根拠について
わかりやすく解説していきます。
私たちの業界では有名な「HEAT20」という
一般社団法人が2021年に発行した
設計ガイドブックに、C値に関する詳細な
記述がありますので、今回はこれに基づいてお伝えします。
気密性能はなぜ必要か?
気密性能の主な目的は以下の4つです。
- 暖冷房の熱負荷の低減と快適性の向上
- 空調効率が上がり、光熱費が削減され、快適な室内環境を実現できます。
- 断熱材の性能保持
- 気密性が高いと、断熱材の性能劣化が抑えられます。
- 壁体内結露の防止
- 繊維系断熱材(グラスウールやロックウールなど)を使う際、気密が重要になります。
- 計画換気の性能維持
- シックハウス対策として導入された24時間換気を機能させるために、気密が不可欠です。
HEAT20の視点:快適性に注目
HEAT20は、気密性を高めることによる
「冬期の冷気(隙間風)の流入防止
=快適性NEB(Non-Energy Benefits)」の
向上を重視しています。

実際に人が不快に感じるのは温度よりも
風速であることが分かっており、
その観点から気密性と快適性の相関が分析されています。
ACHという新しい基準
従来のC値は「床面積」ベースでしたが、
吹き抜け・勾配天井など多様な間取りが
増えた今では、**気積(室内の容積)**で
評価すべきとの流れがあります。

海外では、差圧50Pa時の換気回数(ACH50)が
標準ですが、HEAT20では差圧9.8Paでの
評価(ACH9.8)を提案しています。
具体的には、
ACH9.8 = Q9.8 / ViQ9.8:通気量(㎥/h) Vi:気積(㎥)
この数値が小さいほど気密性が高く、
隙間風も少なくなります。
快適性の科学的根拠
快適性を評価する際、「15%以下の人が
不快と感じる状態」を合格ラインとしています。
室温20℃で風速0.2m/sを超えなければ、
ほとんどの人が快適だと感じる、
という知見に基づいています。

この観点から、気密性能と風速の相関を分析した結果、
- ACH9.8 = 0.5
- C値に換算すると約0.9 が快適性を確保できる基準として妥当であるとされています。
劣化を見越した補正も重要
気密性能は新築時が最良で、
時間が経てば劣化します
(テープの剥がれ、地震などの影響)。

そのため、将来的な劣化を見越して、
さらに厳しい基準として、
- ACH9.8 = 0.4±0.1
- C値 = 0.7±0.2(目安:0.5~0.9) を目標値として設定するのがよいとされています。
C値の目標は「0.5~0.9」
C値が0.1でなければダメ、
ということではありません。
新築時に0.5~0.9の範囲であれば、
十分に快適性と省エネ性を担保できると、
HEAT20が科学的根拠に基づいて示してくれています。
気密測定の結果に一喜一憂するのではなく、
「快適に暮らせる家になっているか?」という
視点でC値を見ていただければと思います。