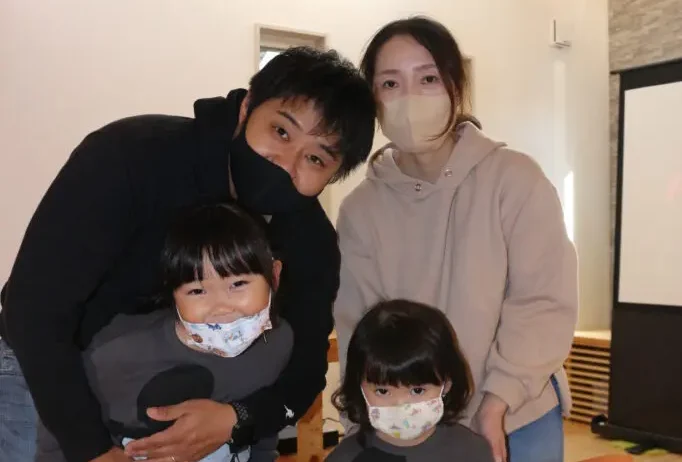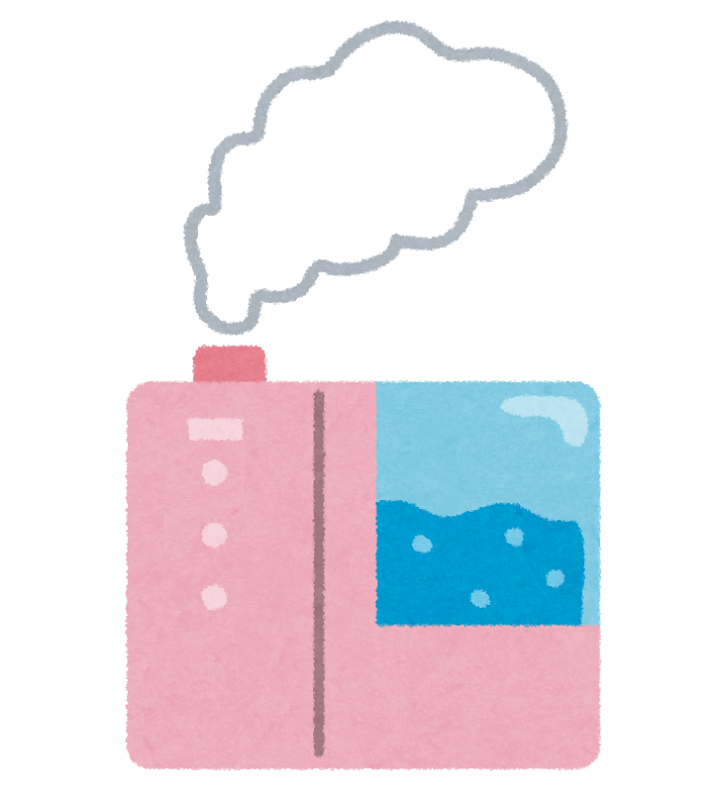家づくりを考えている方から、
断熱材に関する質問をよく受けます。
その中でも今回は、あまり知られていない
「遮熱材」について解説します。

「遮熱シートは使った方がいいのか?」
といった質問をいただくことが多いので、
科学的な基礎知識とともに、
遮熱材のメリット・デメリット、
正しい活用方法について説明していきます。
熱の移動と断熱・遮熱の違い
家の快適性を考える際、
最も重要なのは「熱の移動」です。
断熱材は熱の移動を遅らせる
役割がありますが、
遮熱材は熱の移動そのものを
反射して防ぐ役割を持ちます。
熱の移動には大きく3つのパターンがあります。
1. 熱伝導
熱が物質を通じて移動する現象。
例えば、金属のスプーンを熱いスープに入れると、
スプーンの先端まで熱が伝わるのが熱伝導です。

2. 対流
空気や水が移動することで熱が伝わる現象。
エアコンの風や温かい空気が
上に登っていくのが対流です。

3. 輻射(ふくしゃ)
熱が電磁波(赤外線など)として伝わる現象。
ダルマストーブの前にいると、
直接温かさを感じるのは輻射熱によるものです。

宇宙空間では空気がないのに
太陽の熱が地球に届くのも、
この輻射熱の作用です。
遮熱材の仕組みと特徴
遮熱材は「輻射熱」を反射することで
熱の影響を軽減する材料です。
主に金属膜を使用し、
最も一般的なのは アルミ箔 です。

例えば、宇宙船や人工衛星の表面には、
輻射熱を反射するために金属箔が
使用されています。
アルミ箔は輻射熱を 90〜99%反射
することが可能で、
これを家づくりに応用したのが遮熱材です。
遮熱材の種類
市販されている遮熱材には、
以下の3つのタイプがあります。
1. アルミ蒸着シート
不織布や透湿防水シートに
アルミを蒸着したもの。
有名な商品に 「タイベックシルバー」などがあります。
2. 断熱ボード+アルミ箔
ウレタンフォームなどの断熱材の表面に
アルミ箔を貼ったもの。
代表的な製品には 「アキレス キューワンボード」 があります。
3. バブルポリウレタン型遮熱材
プチプチのような気泡層を持つ遮熱材で、
アルミ箔をプラズマ溶着している複合素材。
有名な商品には 「リフレクティクス」
「アストロホイル」 などがあります。
遮熱材のメリットとデメリット
メリット
- 輻射熱を防ぐ:遮熱材は熱線・冷線を反射し、室内の温度変化を抑えます。
- 紫外線劣化しにくい:アルミは紫外線による劣化が少なく、耐久性が高いです。
- 屋根裏や倉庫の温度を下げる:特に夏場の屋根裏や倉庫では、遮熱材を使用することで劇的に涼しくなります。
デメリット
- コストが高い:一般的な断熱材よりも価格が高めです。
- 熱伝導しやすい:アルミは熱伝導率が高いため、適切な施工が必要です。
- 施工方法に注意が必要:間違った施工では効果がほとんど得られません。
遮熱材の正しい施工方法
遮熱材の効果を最大限に発揮するには、
「空気層の確保」が重要です。

例えば、屋根のすぐ裏にアルミ箔を貼っても、
屋根から伝わる熱が直接アルミに移動し、
反射する効果がほとんど得られません。
しかし、遮熱材の外側に「静止空気層」を確保すると、
輻射熱を反射しやすくなります。
施工のポイント
- 遮熱材と屋根の間に最低でも数cmの空気層を作る
- 空気層は対流が起きないように静止空気層にする
- 断熱材と併用することで相乗効果を発揮する
遮熱材の効果についての実験結果
実際に、ある工務店で以下のような実験が行われました。
- 遮熱材を使用した家
- 断熱材のみを使用した家
同じ条件で比較したところ、
室内の快適性には大きな違いが
なかったという結果が出ました。
つまり、「遮熱材だけでは決定的な違いを生むわけではない」 ということです。
ただし、適切に施工すれば十分な
効果を発揮するため、使い方次第とも言えます。
遮熱材の活用方法
私は、遮熱材を 補助的に活用することを推奨しています。
- 断熱・気密をしっかりと行った上で、補助的に遮熱材を使用する
- 屋根裏収納や改修工事では特に有効
- ペットの小屋など、簡単な遮熱対策にも有効(実際に私の飼っていたコーギーの犬小屋にも使用していたおり、冬場でも快適そうに過ごしていました)

遮熱材は使い方
遮熱材は適切に使えば効果を発揮しますが、
施工方法や環境によっては効果が
得られないこともあります。
そのため、専門知識を持つ施工者と
相談しながら活用するのが理想的です。

「断熱・気密を優先し、遮熱は補助的に」
という考え方が、家の快適性を最大化するポイントです。
皆さんの家づくりの参考になれば幸いです!