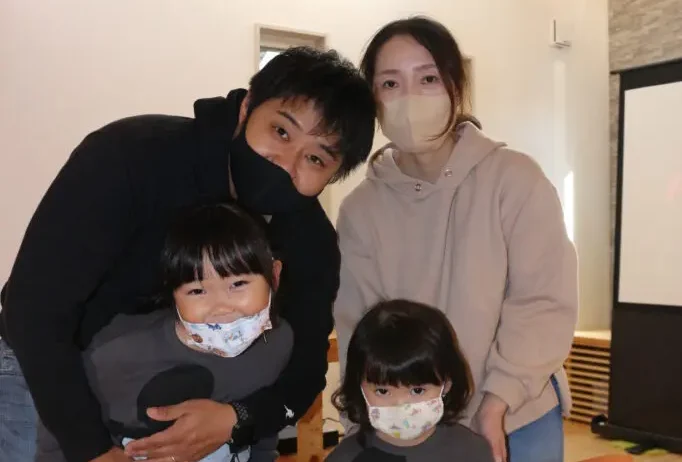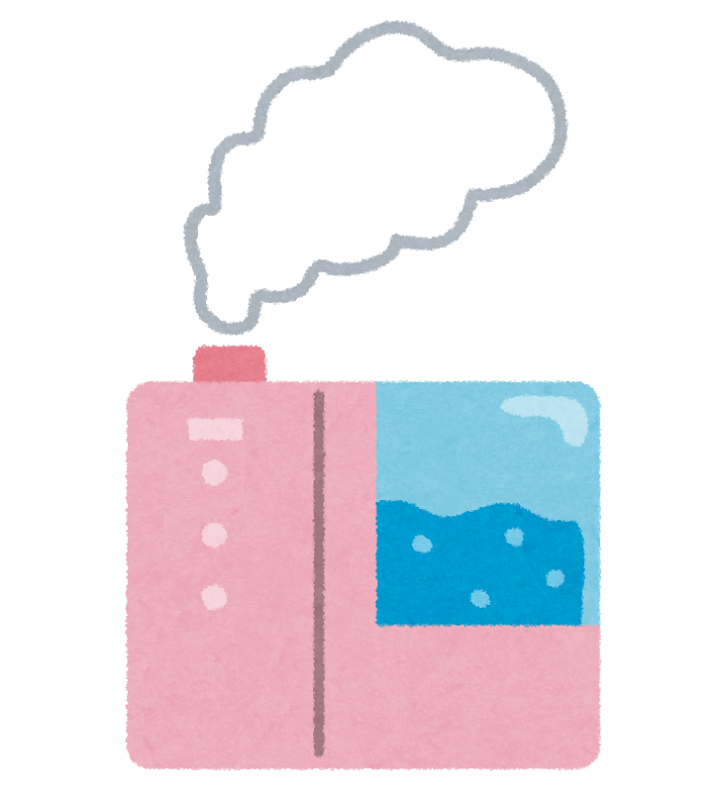60年保証は本当に安心?その仕組みと落とし穴
先日、お客様から「60年保証ができる会社と
契約した方がいいですか?」という質問を受けました。

長期間保証してくれるのは確かに安心感があります。
しかし、私はこの「60年保証」という言葉には、
お客様の不安につけ込んでいる部分もあると
感じています。
今回は、その理由について詳しく解説していきます。
60年保証の仕組みとは?
60年保証とは、引き渡しから10年、20年、30年…と、
長期間にわたって保証するというものです。

しかし、この保証内容は多くの人が
想像するものとは少し異なります。
10年保証と60年保証の違い
住宅業界では「10年保証」という言葉が
昔から存在します。
これは、住宅の品質確保を目的とした
「品確法(住宅品質確保促進法)」に基づいた
保証であり、無料で提供されます。
「品確法」では、
- 構造躯体(基礎・柱・梁)
- 防水(屋根・外壁)
これらに瑕疵が発生した場合、
施工会社が10年間無償で
対応することが義務付けられています。
さらに、施工会社が倒産した場合でも、
**「瑕疵担保履行法」**により、
供託金や保険を利用して補償が
受けられる仕組みになっています。

このように、10年保証は法律によって
義務化されており、誰でも無償で受けられるものです。
しかし、60年保証はこの10年保証の延長ではなく、
全く異なる仕組みで成り立っています。
60年保証の実態
60年保証を受けるには、10年ごとに
有償の点検や修繕を行う必要があります。
例えば、
- 10年目の点検で防水の劣化が見つかる → 修繕が必要(有償)
- 20年目の点検で外壁の塗装が劣化 → 塗り直し(有償)
- 30年目の点検でコーキング材の劣化 → 交換(有償)
このように、
**「保証を延長するための条件として、
有償のメンテナンスが必要になる」**
というのが60年保証の本質です。

特に、大手ハウスメーカーはこの仕組みを
採用していることが多く、
結果的に「イニシャルコストもランニングコストも
高くなる」という現実があります。
クローズド工法とオープン工法の違い
60年保証を強く打ち出しているのは、
大手ハウスメーカーが多いです。
これらの会社の住宅は、**「クローズド工法」**が
採用されていることが多く、
この工法は特定のメーカーでしかメンテナンスや
修理ができません。
一方で、地域の工務店などが採用する
**「オープン工法」**は、
どの会社でも施工・修理が可能です。
クローズド工法のデメリット
クローズド工法の住宅では、
リフォームや修理を行う際に、
同じメーカーに依頼するしかありません。
そのため、
- 相見積もりが取れない(価格の比較ができない)
- 修理費用が割高になる傾向がある
- 特定の部材が必要なため、修理の選択肢が限られる
例えば、私の親戚がクローズド工法の
住宅に住んでおり、修理の見積もりが
400万円だったのですが、
オープン工法で建てた場合なら
150万円~250万円で済むような内容でした。

つまり、**「60年保証があるから安心」ではなく、
その住宅の工法によっては後々のメンテナンス費用が
高くつくことがある」**という点を
理解することが重要です。
60年保証より大切なポイント
60年保証に目を奪われるのではなく、
以下の点に注目してください。
- 免責事項を確認する
- 60年間で何が保証対象外なのか?
- 結露やシロアリなどの対策はどうなっているのか?
- オープン工法かクローズド工法かを確認する
- 将来的な修理やリフォームの自由度が変わる
- 地盤保証の有無を確認する
- 瑕疵担保保険は基礎や躯体のみで、地盤の問題は保証されない
最近の住宅の品質は
日本の住宅の品質は年々向上しており、
専門的知識を持った
知見のある工務店によって
適切な施工がされていれば30年以上
大きな問題なく住み続けることが可能です。
確かに、60年保証は一見すると
安心感があります。
しかし、その実態を理解せずに
契約すると、長期的に見てコストが
膨らむ可能性があるのです。
大切なのは、
- 60年保証という言葉に惑わされないこと
- 家の品質を左右する施工のポイントを理解すること
- 地盤保証やメンテナンスの実態を確認すること
家を建てる際は、「60年保証」の有無よりも、
**「信頼できる施工と適切なメンテナンスが
可能な会社を選ぶこと」**が最も重要です。

皆さんが後悔しない家づくりをできるよう、
ぜひ慎重に検討してください。