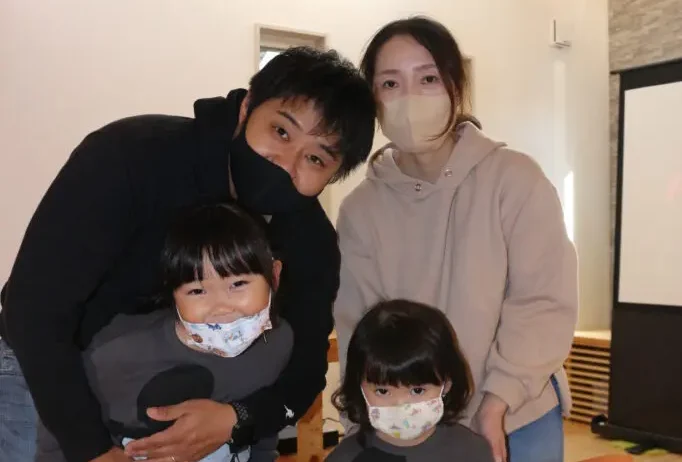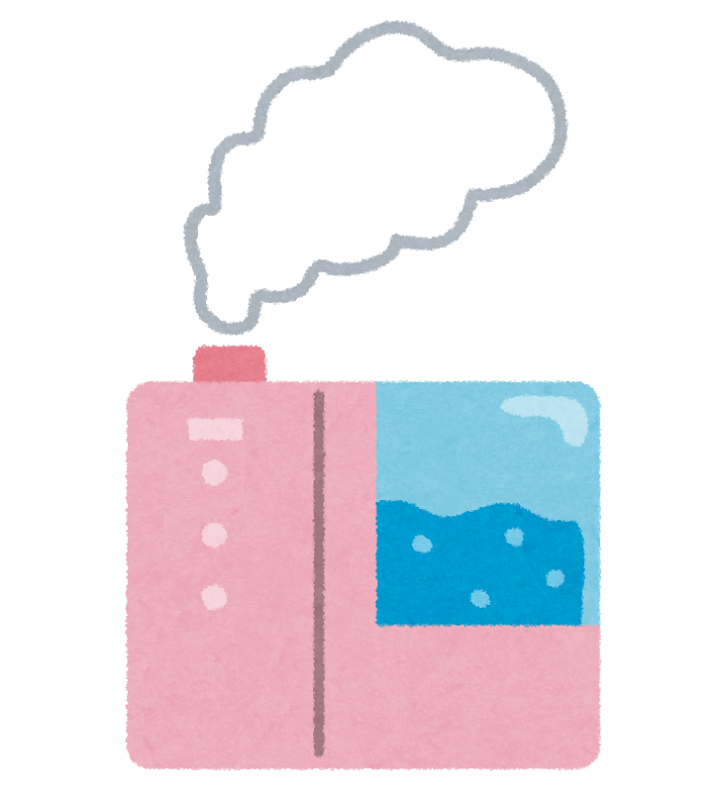巷でよく話題に上がる、
「塗り壁にすると冬の乾燥や結露がなくなる」
という現象が本当に起こるのかどうかについて、
私なりの考えをお話しします。
きっかけはお客様の質問から
先日、お客様からこんな相談を受けました。
冬の乾燥が嫌で加湿すると、今度は結露が気になります。ある業者さんに「内壁を塗り壁にすれば調湿性能があるので乾燥も結露も気にしなくていい」と言われました。塗り壁にした方がいいんですか?
この質問をきっかけに、冬の乾燥や結露のメカニズム、
そして塗り壁の効果について考えてみました。

冬の乾燥のメカニズム
まず、冬の乾燥の原因を考えてみましょう。
現在、24時間換気システムが義務付けられており、
外の空気が常に家の中に取り込まれます。

外気温が低い冬、外の空気に含まれる
水蒸気量(絶対湿度)は非常に少ない状態です。
これが家の中に入ると、室内の空気は乾燥します。
例えば、1月の本州の温暖な地域では
平均気温が約6.1℃、相対湿度は49%です。
一見湿度が高そうに思えますが、
絶対湿度で見ると、
空気の重さ1kg(約1.2㎥)中に
含まれる水蒸気量はわずか約2.9g。
この数値は、快適と感じる5月や10月の
絶対湿度(約8.8g)と比べると圧倒的に少ないです。

つまり、冬の乾燥は避けられない現象なのです。
塗り壁の調湿性能と乾燥対策
業者さんの説明では、塗り壁には調湿性能があり、
人が発する水蒸気を吸収して保持し、
必要に応じて放出することで乾燥を
和らげるとのことです。
しかし、絶対湿度2.9gから快適な7g以上に
引き上げるには相当な水蒸気量が必要です。
例えば、30坪の住宅(天井高2.4m)を、
2.9gから7gに加湿する場合、
必要な加湿量は、
30坪×3.305785=99.17㎡
99.17㎡×2.4m=238.01㎥(室内の容積)
1日24時間の入れ替わる空気量が
238.01㎥×24時間×0.5=2856.12㎥
必要な加湿量は、
(7-2.9)g×2856.12㎥÷0.83=14108g→14.1kg
一日の加湿量が14ℓ以上必要になります。
加湿器を使用しても大変な量です。
これだけの量を塗り壁から放出することは
不可能だと分かります。
つまり、外気による乾燥した空気が家の中に
常に流入する以上、塗り壁だけでは
乾燥を解消するのは難しいでしょう。
乾燥対策としては、加湿器を利用するのが現実的です。

冬の結露のメカニズム
次に結露についてです。
結露は、水蒸気を含んだ暖かい空気が
冷たい表面に触れて発生します。

特に壁の中での結露(壁体内結露)は、
断熱材や構造材にダメージを与えるため厄介です。
一般的に塗り壁を採用する家では、
セルロースファイバーという
断熱材が使われることが多いです。
この断熱材は調湿性能があり、
水分を保持しつつ壁内の湿度を調整する
役割を果たします。
しかし、塗り壁や断熱材の調湿性能だけで
壁体内結露を完全に防ぐことは難しいです。
結露を防ぐための2つの防波堤
結露を防ぐには、以下の2つの防波堤を設けることが重要です。
- 気密シートで水蒸気の侵入を防ぐ 室内側の石膏ボードの裏にポリエチレン製や可変透湿型の気密シートを設置し、水蒸気が壁内に侵入するのを防ぎます。
- 透湿性のある素材で水蒸気を速やかに排出 万が一壁内に水蒸気が入り込んだ場合、耐力面材や防水シートを透湿性の高い素材にして水蒸気を外へ逃がします。
これらの対策を組み合わせることで、
結露のリスクを大幅に軽減できます。
塗り壁の限界と結論
塗り壁は確かに調湿性能を持ちますが、
それだけで冬の乾燥や結露を完全に
解決するのは難しいです。
特に、結露を防ぐには塗り壁の効果を過信せず、
適切な気密処理と換気対策が必要でをす。
また、冬の結露対策として忘れては
いけないのが「窓」です。

窓は結露が最も発生しやすい場所であり、
塗り壁とは関係ありません。
高性能な断熱窓や複層ガラスを採用することが、
結露を防ぐために非常に重要です。
塗り壁は
塗り壁は風合いやデザイン性の
高さから人気がありますが、
乾燥や結露の解決策としては過信せず、
基本的な建築対策を施すことが大切です。
乾燥対策には加湿器、結露対策には
気密シートや高性能な窓を取り入れるなど、
バランスの取れた方法を検討してください。

塗り壁の魅力を楽しみつつ、
しっかりとした対策で快適な住環境を目指しましょう。
ぜひ参考にしてみてください!